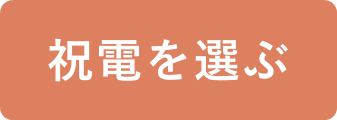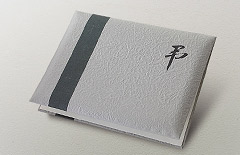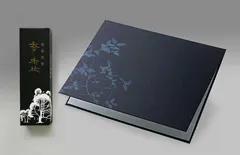初めての弔電ガイド|初心者でも安心の送り方・文例・マナー解説
「弔電ってどうやって送るの?」「何を書けばいいの?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
初めて弔電を送る方に向けて、このページでは弔電の意味・送り方・マナー・文例まで、初心者でも安心して手配できるようにわかりやすく解説します。
葬儀や法要などで弔意を伝える際の参考に、ぜひご活用ください。
弔電とは?初心者にもわかりやすく解説
弔電とは、葬儀・通夜・法要などの場に弔意の言葉を届ける電報のことです。
直接参列できない場合や急な訃報で駆けつけられない場合に、故人やご遺族への思いを丁寧なメッセージで伝える手段として利用されます。
形式と心を大切にする日本独自の弔意表現として、現在でも多くの方に選ばれ続けています。
弔電を送るタイミングと手続きの流れ
通夜・葬儀それぞれの目安
弔電は、通夜または告別式の前までに届くように送るのが一般的です。
特に通夜に間に合えば、遺族に早く気持ちを届けることができ、より丁寧な印象を与えられます。
告別式に向けて送る場合も、開始時刻の前までに到着するよう余裕をもって手配することが重要です。
当日配達に間に合わせるコツ
訃報を受けたら、できるだけ早く手配を始めましょう。
電報サービスの中には、当日14時までの注文で即日配達が可能なものもあります。
「送りたいと思ったその時」にすぐ注文できるよう、弔電の利用タイミング解説ページも併せてご確認ください。
宛名と差出人の正しい書き方
喪主・ご遺族への宛名マナー
弔電の宛名は、喪主様宛にするのが基本です。
名前の後に「様」を付けて表記し、フルネームを使用するのが丁寧な書き方とされています。
喪主の名前が不明な場合は、「○○家ご遺族様」といった表現を使うこともあります。
法人・会社から送る場合の書き方
差出人欄には、会社名・役職・氏名を明記すると、ビジネスマナーとしても信頼性が高まります。
たとえば「株式会社○○ 代表取締役 山田太郎」のように記載します。
個人として送る場合も、関係性を一言添えるとご遺族に安心感を与えることができます。
弔電で使ってはいけない言葉(忌み言葉)
避けるべき言葉の具体例
弔電では、不幸の繰り返しや死を連想させる表現は避けるのがマナーです。
たとえば、「ますます」「再び」「たびたび」などの重ね言葉や、「死亡」「急死」など直接的な死の表現は控えるのが礼儀とされています。
代替表現の例
不適切な表現を避けるためには、柔らかく配慮ある言葉に置き換えることが大切です。
たとえば「ご冥福をお祈りします」の代わりに「安らかな旅立ちでありますようお祈り申し上げます」といった表現が用いられることもあります。
宗教や地域によっても適切な言葉が異なるため、文面を選ぶ際は慎重に検討しましょう。
▶ 詳しい忌み言葉の一覧はこちらをご覧ください
宗教ごとの表現マナーにも注意
仏教|「ご冥福」が使える場合と使えない場合
仏教では「ご冥福をお祈りします」という表現が一般的に使われますが、浄土真宗では死後の冥福という考えがないため、この表現は避けるのが通例です。
宗派によっても受け止め方が異なるため、念のため文面には配慮しましょう。
神道|故人は「神様」になる
神道では、亡くなった方は「神」となり、祖霊として祀られるとされています。
そのため「ご冥福」や「成仏」など仏教的な表現は避け、「安らかな眠り」や「静かな旅立ち」といった表現が適しています。
▶ 神道の弔電マナーを詳しく見る
キリスト教|「天国での安らぎを」などが一般的
キリスト教では、「天国での永遠の平安をお祈りします」「主の御許で安らかに」などの表現が使われます。
「冥福」や「成仏」などの仏教語は使用せず、信仰に合った言葉を選ぶことが大切です。
▶ キリスト教の弔電表現はこちら
宗教・宗派がわからない場合の無難な表現
宗教が不明な場合は、「心よりお悔やみ申し上げます」や「安らかな眠りをお祈りいたします」といった宗教色を避けた表現が無難です。
一般的な弔意を伝える文面であれば、どの宗教にも配慮した形となります。
▶ その他の弔電マナーや文例は、弔電のご案内ページをご覧ください。
初めての方でも使いやすい弔電の文例
弔電の文章では、「どのように書けばよいか分からない」「失礼にならない言葉を選びたい」と不安を感じる方も多いでしょう。
以下に、初めて弔電を送る方にも使いやすいシンプルで丁寧な文例をご紹介します。
親族・親戚向けの文例
ご逝去の報に接し、深い悲しみを覚えております。
ご家族の皆様には、心よりお悔やみ申し上げます。
友人・知人向けの文例
突然の訃報に接し、ただ驚いております。
安らかなご永眠を、心よりお祈り申し上げます。
会社・上司・取引先向けの文例
ご尊父様のご逝去に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご遺族の皆様のご平安を心よりお祈りいたします。
上記は一例ですが、続柄や立場に応じた文例をさらにご覧いただけます。
▶ 弔電の文例集をもっと見る
▶ 弔電全体のご案内ページはこちら
初心者に人気の弔電商品の選び方
形式(台紙・線香・供花付き)の違い
初めて弔電を送る方には、シンプルで落ち着いた台紙タイプが基本として選ばれています。
さらにお線香付きや供花付きといった贈答品がセットになったタイプも人気で、気持ちをより丁寧に伝えたい場面でよく選ばれています。
形式によって印象が異なるため、状況に応じた選び方が大切です。
たとえば、台紙だけの弔電は形式重視の葬儀全般に適しており、お線香付きは仏教の方への贈り物に、供花付きは遠方からの気持ちをより強く伝えたいときにおすすめです。
予算ごとのおすすめ目安
3,000円〜5,000円台の商品が最も選ばれており、初めてでも失礼のない価格帯として安心です。
ご予算や贈る相手との関係性に合わせてお選びいただけます。
▶ お線香付き弔電の特集ページはこちら
▶ 供花付き弔電の選び方ガイド
▶ 弔電の総合案内ページを見る
初めての弔電に選ばれている商品
初めて弔電を贈る方に向けて、特に人気の高い商品を厳選してご紹介します。
台紙タイプから線香付き、和紙を用いた格式ある電報まで、安心して選べるラインアップです。
▶ すべての弔電商品を見る
弔電の送り方・マナー・文例までまとめて知りたい方は、弔電ガイド総合ページもご活用ください。
よくある質問|初めて弔電を送る方のために
弔電はどのタイミングで送れば間に合いますか?
-
通夜または告別式に間に合うように手配するのが一般的です。
訃報を受けたら、できるだけ早めに手続きしましょう。
当日配達が可能な電報サービスもありますので、急な場合でもご安心ください。 誰に宛てて送るのが正しいですか?
-
通常は喪主またはご遺族の代表者を宛名にします。
お名前がわからない場合は、「○○家 ご遺族様」としても失礼にはあたりません。 文例をそのまま使ってもよいですか?
-
はい、大丈夫です。弔電の文例は多くの方が利用しており、失礼のない表現として安心して使えます。
▶ 弔電文例集はこちら 宗派が分からないときはどうすればいい?
-
宗派がわからない場合は、宗教色のない言い回しや無難な表現を選ぶのがマナーです。
例:「心よりお悔やみ申し上げます」「ご遺族の皆様のご平安をお祈りいたします」など。 急ぎの場合、即日対応はできますか?
-
はい、当日14時までのご注文で即日配達可能な商品もございます。
詳しくは各商品ページにて「即日対応可」の表示をご確認ください。
弔電マナーをもっと詳しく知りたい方へ
初めて弔電を送る方はもちろん、宗教ごとのマナーや文例選び、贈り方の注意点まで詳しく知りたい方は、
以下の総合ガイドをご覧ください。