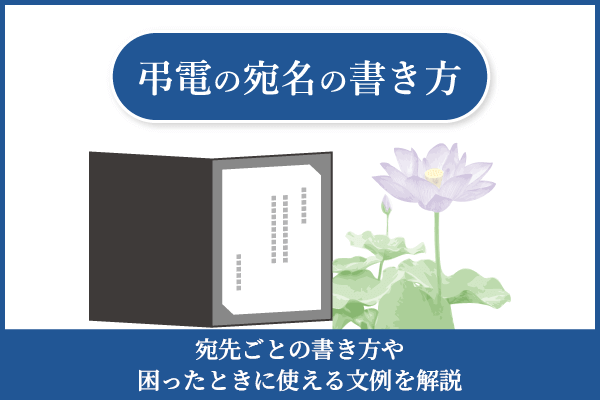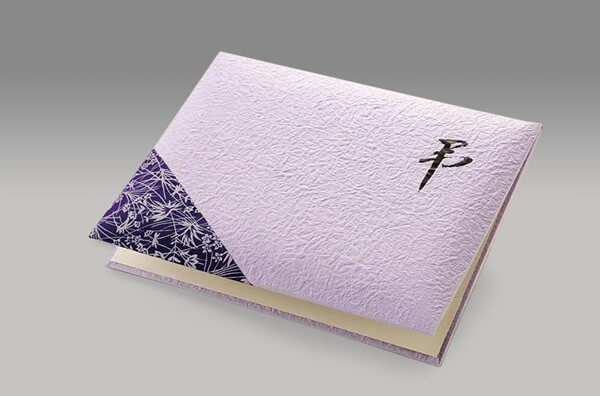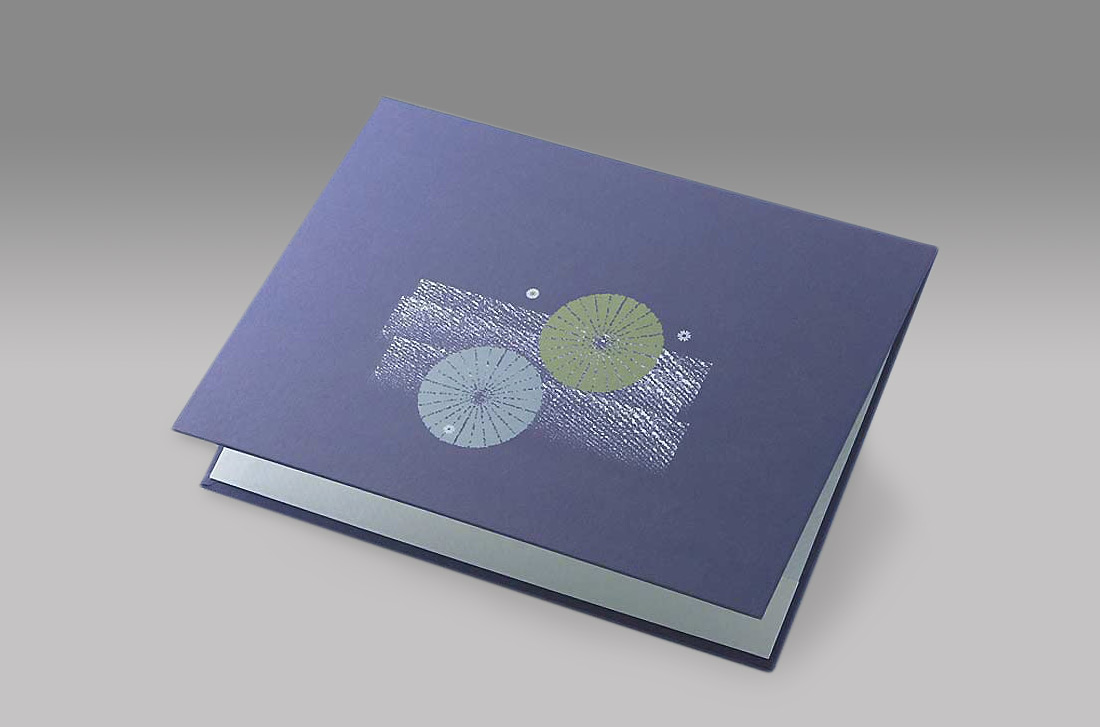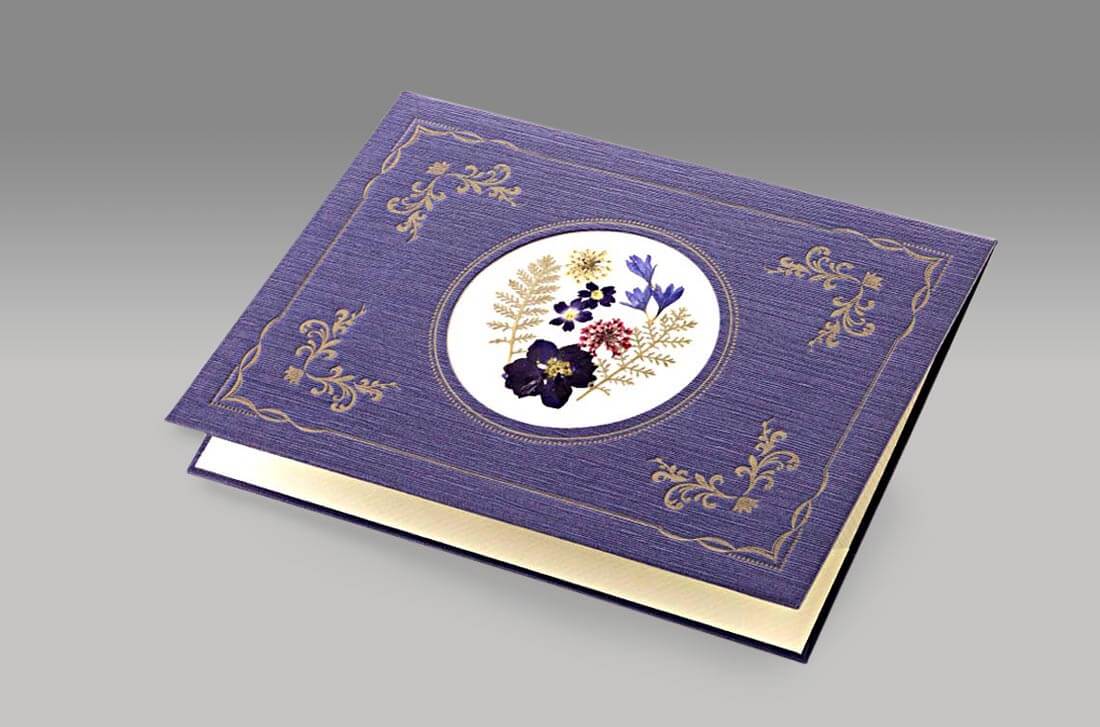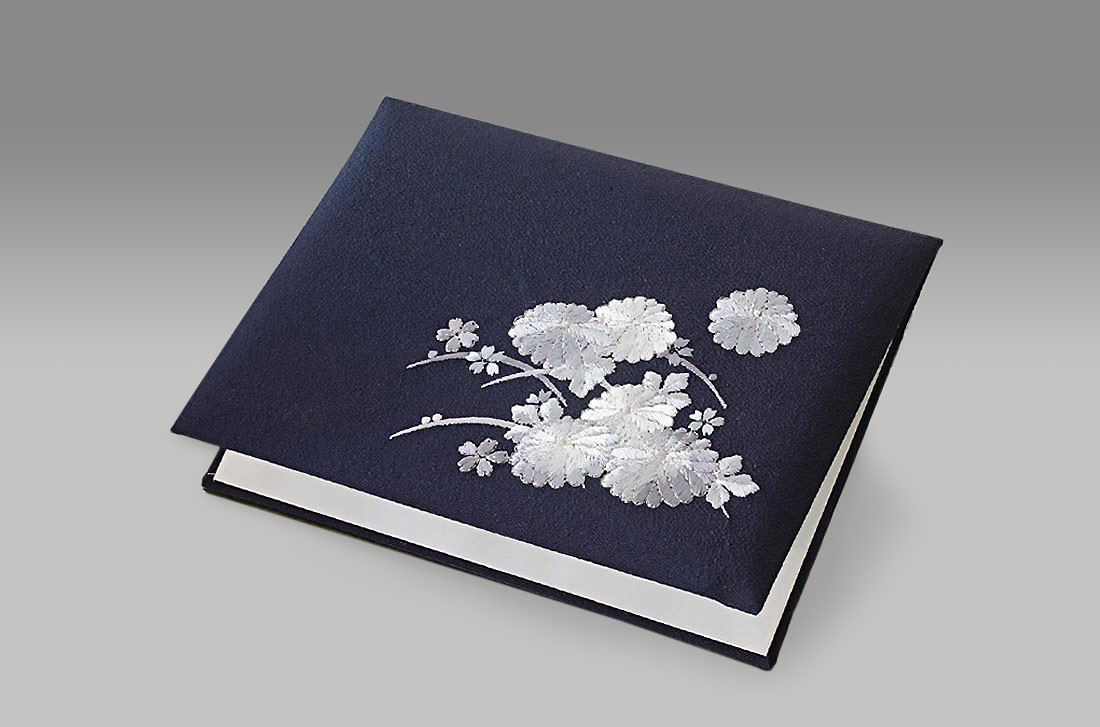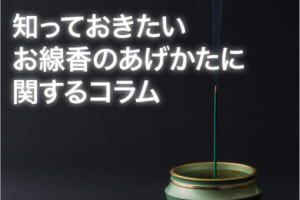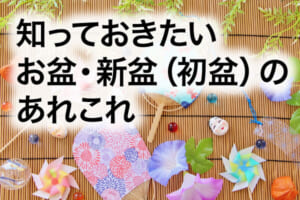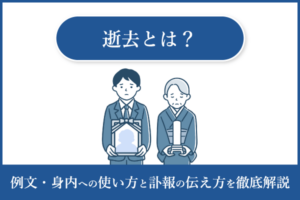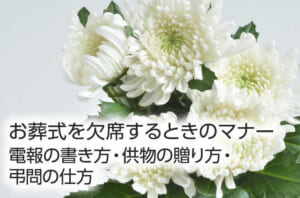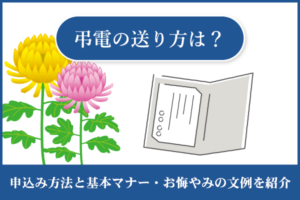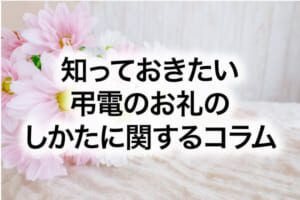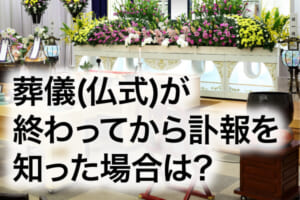「弔電の宛名の書き方は?」
「弔電はどこに届ける?」
弔電の宛名の書き方は、「喪主の名前をフルネームで記載する」のが基本マナーです。
通夜や葬儀の場面では、宛名の書き方ひとつで遺族への敬意や配慮が伝わります。
とはいえ「喪主がわからない場合は?」「喪主以外の遺族に届けたいときは?」など、いざ電報を送ろうとすると迷うことも少なくありません。
本記事では、弔電の宛名の正しい書き方を解説し、困ったときに使える具体的な文例も紹介します。
差出人の情報をどう書けばよいか、お悔やみの気持ちを失礼なく届けるためのポイントもあわせて確認しましょう。
弔電とは?
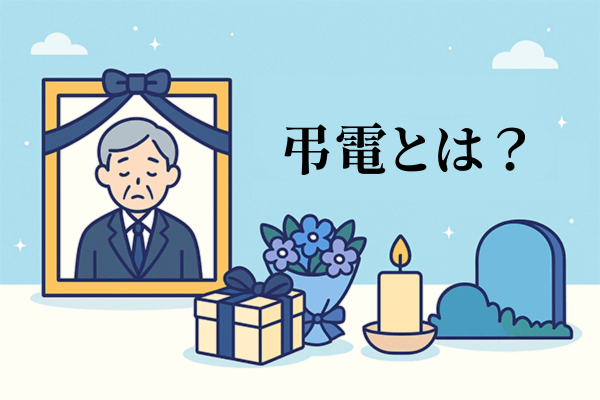
弔電とは、葬儀や告別式に直接参列できない場合に、遺族に対して哀悼の気持ちを伝える電報のことを指します。
仕事の都合や距離の問題で参列が難しいときでも、弔電を送ることで故人への追悼の意を表し、遺族に寄り添う気持ちを届けられます。
本項では以下の2つに分けてさらに解説します。
- 弔電の役割
- 弔電を送るタイミング
弔電には決まった形式があり、文面には丁寧な言葉遣いが求められます。
形式を守ることで、相手に誠意が伝わりやすくなるのです。
以下でそれぞれ詳しく解説していきます。
弔電の役割
弔電の役割は、故人を悼む気持ちと遺族へのお悔やみの意を伝えることにあります。
直接顔を合わせられない場合でも、弔電を通じて心を届けることで、遺族に安心感や支えを与えることができます。
また、弔電は形式が整ったメッセージとして扱われるため、社会的な礼儀を果たす意味合いも強いといえるでしょう。
弔電は遺族にとって故人を偲ぶ大切な形見となることがあります。
葬儀後に読み返すことで、多くの人が故人を思ってくれたことを実感でき、悲しみに寄り添う力にもなるのです。
弔電は単なる文章のやり取りではなく、心を形にして届ける大切な役割を果たしています。
弔電を送るタイミング
弔電は、通夜や葬儀が始まる前までに届くように手配するのが基本マナーです。
式の場で読み上げられることも多いため、できるだけ早く手続きを行い、葬儀の当日までに確実に届けるようにしましょう。
訃報を知ったら、できればその日のうち、遅くとも通夜や葬儀の前日までに手配するのが望ましいとされています。
直前になってしまうと、葬儀当日に間に合わない場合があるため注意が必要です。
もし事情があって葬儀までに弔電を送れなかった場合は、四十九日法要などの節目に合わせて改めてお悔やみの言葉を伝える方法もあります。
遅れてでも気持ちを伝えることが、遺族にとっては大切な慰めとなります。
よく選ばれている弔電
弔電の宛名の書き方
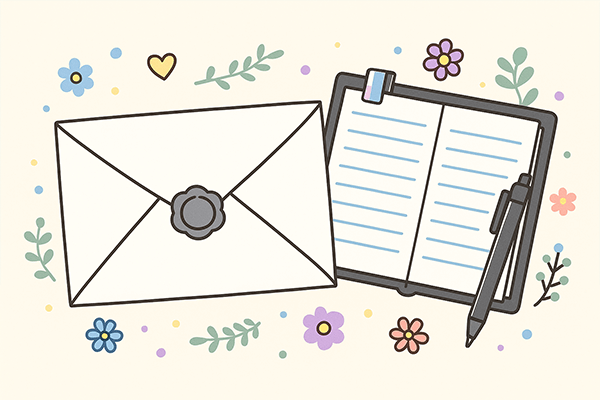
弔電の宛名は、喪主の名前をフルネームで記載するのが基本マナーです。
葬儀や通夜では同じ会場で複数の葬儀が行われることもあるため、名字だけでは判別がつかない場合があるので、必ずフルネームで書くようにしましょう。
また、宛名には 「様」 を必ず付けます。
弔電は遺族や故人へのお悔やみの気持ちを正式に伝えるものなので、敬称を省略するのは失礼にあたります。
基本的な弔電の宛名の書き方の例は、以下とおりです。
- 喪主 山田 太郎 様
- 喪主 佐藤 花子 様
次に説明する「喪主がわからない場合」の書き方もあわせて確認し、状況に応じて失礼のない弔電を送るようにしましょう。
喪主がわからない場合の宛名の書き方
弔電を送るときに「喪主の名前がわからない」というケースは少なくありません。
葬儀や通夜では、弔電の宛名は本来 喪主のフルネームを記載するのが基本マナーですが、喪主が確認できない場合でも失礼にならない記載方法があります。
もっとも一般的なのは、故人の名前を使った宛名にする方法で、以下のように書きます。
- (故 ○○ ○○ 様)ご遺族様
- (故 ○○ ○○ 様)ご親族一同様
上記のように「故人の名前+ご遺族様」という表現を用いれば、葬儀会場や斎場でも確実に誰宛の弔電か判断でき、混乱を防ぐことができます。
生花や供物がセットになった弔電
【弔電の宛名の書き方】喪主以外に送る場合
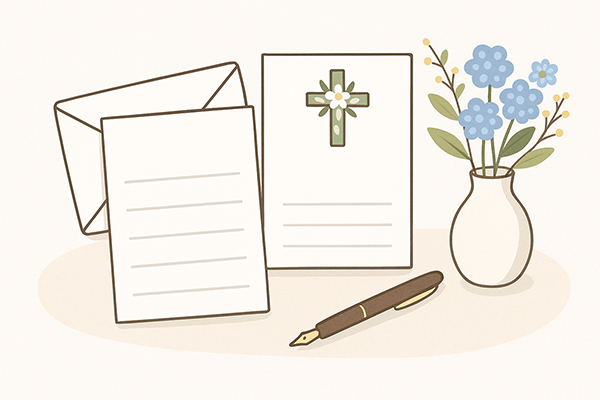
弔電の宛名を喪主以外にする場合の書き方について、以下の2つのパターンを紹介します。
- 喪主以外の遺族に送る場合
- 社葬に送る場合
弔電は基本的に喪主宛に送るのが一般的ですが、状況によっては喪主以外に宛てたい場合もあるでしょう。
たとえば、故人と特に親しかった遺族に直接お悔やみの気持ちを伝えたいときや、会社や団体が執り行う社葬に電報を送るときです。
具体的な宛名の記載方法を解説しますので、参考にしてください。
喪主以外の遺族に送る場合
弔電を喪主以外の遺族に届けたい場合でも、宛名は喪主を主に書くのが基本マナーです。
弔電の仕分けは喪主宛が基準となるため、喪主名を宛名にしたうえで、本文や備考欄で「〇〇様へお取り次ぎ願います」と記載するのが確実です。
〒123-4567
〇〇斎場 気付
喪主 山田 太郎 様
(ご長男 山田 一郎 様へお取り次ぎ願います)
上記のように書けば、弔電は正しく会場で仕分けされ、希望する遺族の方に渡してもらうことができます。
社葬に送る場合
社葬や団体葬に弔電を送るときは、通常の個人葬と異なり、会社や葬儀委員会宛にするのが一般的です。
社葬は企業や団体が主体となって執り行うため、喪主個人ではなく「組織」に対して弔電を届ける形がふさわしいとされています。
宛名の書き方としては、以下のような表現がよく用いられます。
- 株式会社〇〇 葬儀委員会 御中
- 株式会社〇〇 代表取締役 △△ △△ 様
また、社葬では参列者や弔電の数が非常に多くなるため、宛名や宛先を正確に記載することが重要です。
必ず案内状に記載された正式名称・住所をそのまま書き写し、必要に応じて「気付」を付け加えるようにしましょう。
弔電の書き方のマナーと注意点
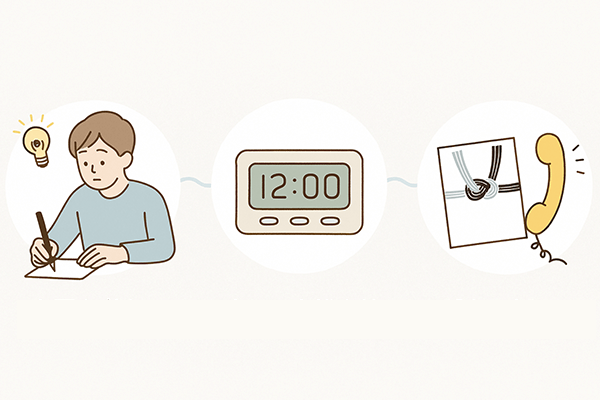
弔電の書き方のマナーと注意点は以下のとおりです。
- 差出人情報を詳細に書く
- 弔事特有の敬称で書く
- 忌み言葉を使用しない
- 弔電の送り先は葬儀場にする
弔電には、特有の敬称や忌み言葉など、気をつけておくべきマナーがあります。
それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。
差出人情報を詳細に書く
弔電を送る際には、差出人情報を詳細に記載することが大切です。
差出人が明確でないと、受け取った遺族が誰からの弔意なのか判断できず、失礼にあたる可能性があります。
特に、同姓同名の可能性がある場合や、普段から交流が少ない相手に送る場合は注意が必要です。
基本的には、氏名をフルネームで記載し、さらに必要に応じて住所や電話番号、会社名や部署名を加えるのが望ましい方法です。
例えば、仕事関係で送る場合は「株式会社○○ 営業部 山田太郎」といった形にすることで、相手がすぐに差出人を把握できます。
また、家族や親戚であっても、世帯単位で送る場合には「○○家一同」と明記するなど、分かりやすい表記を心がけるとよいでしょう。
こうした配慮により、遺族に安心して受け取ってもらえる弔電となります。
弔事特有の敬称で書く
弔電の文面では、日常的な呼び方ではなく、弔事特有の敬称を使うのがマナーです。
弔電で用いられる敬称は、以下のとおりです。
| 故人と喪主(受取人)との関係 | 故人の敬称 |
|---|---|
| 喪主の実父 | ご尊父様 お父様 |
| 喪主の実母 | ご母堂様 お母様 |
| 喪主の祖父 | ご祖父様 お爺様 |
| 喪主の祖母 | ご祖母様 お婆様 |
| 喪主の妻(夫)の 父親 | ご岳父様 お義父様 |
| 喪主の妻(夫)の 母親 | ご岳母様 ご丈母様 |
| 喪主の配偶者 | ご主人様 ご令室様 |
| 喪主の兄弟姉妹 | ご令兄様 ご令弟様 ご令姉様 ご令妹様 |
上記の敬称を正しく使うことで、形式を整えつつ、故人や遺族に対して最大限の敬意を込めたお悔やみの気持ちを伝えることができます。
忌み言葉を使用しない
弔電の文面を作成する際には、忌み言葉を避けることが重要です。
忌み言葉とは、不幸が繰り返されることを連想させる表現や、死を直接的に表す言葉のことを指します。
遺族の心情を傷つける恐れがあるため、十分に注意が必要です。
代表的な忌み言葉には、「重ね重ね」「再び」「またまた」「追って」「次々と」などの重複や継続を連想させる言葉があります。
また、「死ぬ」「生きる」といった直接的な表現も避け、代わりに「ご逝去」「お亡くなりになる」などの敬語表現を用いるのが望ましいです。
弔電は遺族への思いやりを形にしたものです。
忌み言葉を避け、落ち着いた丁寧な表現を選ぶことで、心からの弔意を適切に伝えることができます。
弔電の送り先は葬儀場にする
弔電を送る際は、送り先を喪主の自宅ではなく葬儀場に指定するのが一般的なマナーです。
通夜や葬儀の場には多くの弔電が届くため、会場でまとめて受け取り、式の中で読み上げられる体制が整えられています。
一方、自宅に送ってしまうと受け取りが間に合わず、葬儀当日に読んでもらえない場合があります。
そのため、弔電は必ず葬儀場宛てに送るようにしましょう。
送り先を葬儀場に指定するのは、円滑な進行への配慮であると同時に、遺族に対する思いやりでもあるのです。
弔電の文例
弔電の文例は、送る相手との関係性によって選び方が異なります。
形式を守りつつも、状況に合わせて適切な表現を選ぶことが大切です。
以下に代表的な文例をまとめます。
| 送る相手 | 文例のポイント | 使用例 |
|---|---|---|
| 親族 | 故人を偲ぶ言葉と、遺族をいたわる気持ちを込める | 「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご家族の皆様におかれましては、どうぞご自愛ください。」 |
| 友人・知人 | 個人的な関わりを交えつつ、簡潔にまとめる | 「突然の訃報に接し、ただ驚いております。安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます。」 |
| 会社関係 | 公的で礼儀正しい表現を重視する | 「○○様のご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。ご遺族の皆様のご平安をお祈り申し上げます。」 |
弔電は長文にする必要はなく、簡潔でも誠意の伝わる内容で十分です。
相手の立場を考え、場にふさわしい表現を選ぶことが、失礼のない弔意を届けることにつながります。
弔電の宛名の書き方に関する質問集
弔電の宛名の書き方に関する質問集を紹介します。
- 弔電の宛名は故人名ですか?
- 弔電の宛名の「気付」とは?
- 弔電を連名で送る場合の差出人の書き方は?
弔電の書き方に関する疑問点を放置したまま送ってしまうと、知らず知らずのうちにマナー違反になったり、せっかくのお悔やみの気持ちが正しく伝わらない可能性もあります。
以下に質問と回答を紹介しますので、参考にしてください。
弔電の宛名は故人名ですか?
弔電の宛名を故人の名前にするのは正しい書き方ではありません。
弔電は故人に直接届けるものではなく、葬儀や通夜を取り仕切る喪主やご遺族に宛てて送るものだからです。
葬儀の場では弔電が読み上げられることも多く、宛名が故人名になっていると形式を欠き、受け取る遺族にも違和感や失礼な印象を与えてしまう可能性があります。
喪主が不明な場合も、あくまで「ご遺族様」とするなど、遺族に宛てる形が望ましいとされています。
遺族に失礼のないよう、宛名は必ず喪主やご遺族を基準に記載しましょう。
弔電の宛名の「気付」とは?
弔電の宛名に使われる「気付(きづけ)」とは、宛名本人が実際に住んでいる場所や直接管理している住所ではない場所に、荷物や文書を届けてもらうための補助的な表記のことです。
葬儀では、弔電を自宅ではなく葬儀会場や斎場に送るのが一般的です。
その際、会場は喪主や遺族の住所ではありませんから、弔電を確実に喪主へ届けてもらうために「〇〇斎場 気付 喪主 △△ △△ 様」と記載します。
「気付」を入れることで、斎場や葬儀社のスタッフが一旦受け取り、その後喪主に取り次ぐという流れが明確になり、弔電が滞りなく渡るようになります。
弔電を連名で送る場合の差出人の書き方は?
弔電を友人グループや会社の同僚など複数人で送る場合は、宛名はあくまで喪主やご遺族宛とし、差出人の欄を連名にするのが正しいマナーです。
少人数であれば「佐藤太郎、鈴木花子」のように全員のフルネームを並べて記載します。
人数が四、五人以上になると名前をすべて書くと煩雑になるため、「山田一郎 ほか三名」といった書き方にするとすっきりします。
さらに十名以上の大人数や団体で送る場合は、「株式会社〇〇 営業部一同」や「△△大学 △△ゼミ一同」とまとめると、誰からの弔電かが一目でわかり、受け取る側にも配慮のある書き方になります。
弔電の宛名の書き方に迷ったら「フォー電報」を活用しよう

弔電の宛名や宛先の書き方に迷ったときは、電報サービス「フォー電報」を活用するのがおすすめです。
フォー電報の公式サイトには、喪主宛やご遺族宛など、正しい宛名・宛先の記載例がわかりやすくまとめられています。
さらに、弔電商品も豊富に取りそろえており、シンプルなベーシックタイプから胡蝶蘭やプリザーブドフラワーを添えた高級感のある電報まで幅広く選べます。
- 総務省より特定信書便事業許可を取得している
- インターネットで24時間申込みができる
- 電報の文字料金が無料
- 品質の高い電報商品を揃えている
- アレンジできる文例が豊富
弔電の文例も幅広く揃えていますので、相手に失礼なく、心のこもったお悔やみを確実に届けることができます。
まとめ
弔電の宛名は、喪主のフルネームに「様」を付けて記載するのが基本マナーです。
喪主が不明な場合や社葬など特別なケースであっても、受け取る側が正しく判断できる宛名を心がけることが大切です。
また、宛先は自宅ではなく葬儀場を指定し、必要に応じて「気付」を使うことで、確実に遺族のもとに届きます。
敬称や表現を誤らず、状況に応じた正しい宛名の書き方を選ぶことで、故人や遺族への礼を尽くすことができます。
当記事を参考に、葬儀の場面で失礼のない対応ができるようにしましょう。