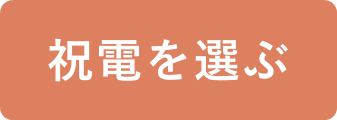弔電で避けるべき忌み言葉・NG表現一覧|失礼のない文面にするための完全ガイド
弔電を送る際、「どの言葉を使えばいいか分からない」「失礼のない表現が知りたい」と悩む方は多くいらっしゃいます。
特に繰り返し・不幸・死・終わりを連想させるような「忌み言葉」やNG表現は、ご遺族の心情を考慮すると避けるべき重要なマナーとされています。
このページでは、弔電で使ってはいけない表現をカテゴリ別に一覧で解説するとともに、安心して使える言い換え例や正しい文例のポイントもあわせてご紹介します。
初めて弔電を送る方でも、文面に迷わず相手に配慮したお悔やみの気持ちを届けられるよう、わかりやすくまとめています。
1. 忌み言葉とは?弔電における意味と重要性
忌み言葉(いみことば)とは、死や不幸、別れ、終わりなどを連想させる言葉や、繰り返しを意味する表現のことを指します。
たとえば「たびたび」「くれぐれも」「死ぬ」「終わる」などは、不幸が続く印象や不吉なイメージを与えるため、弔電では避けるのが一般的なマナーです。
弔電は、ご遺族への哀悼の気持ちを丁寧に伝えるための大切なメッセージです。
言葉の選び方ひとつで印象が変わるため、配慮のある表現を心がけることが大切です。
忌み言葉を避け、落ち着いた表現や宗教・立場に配慮した文面にすることで、失礼のない誠意ある弔意を届けることができます。
2. 弔電で絶対に避けたい忌み言葉・NG表現の一覧
ここでは、弔電で避けるべき忌み言葉を4つの分類に分けてご紹介します。
それぞれの言葉の例・避ける理由・代替表現を併せて確認し、失礼のない文面づくりの参考にしてください。
2-1. 不幸が繰り返されることを連想させる言葉(重ね言葉)
「たびたび」「くれぐれも」などの重ね言葉は、不幸が続くことを連想させるため、弔電では使用を避けましょう。
- NG表現:たびたび/重ね重ね/くれぐれも/いよいよ/次々
- 代替表現:深く/心より/慎んで/このたびは
2-2. 死や終わりを直接的に連想させる言葉
「死ぬ」「終わる」などの直接的な表現は、ご遺族への配慮を欠く恐れがあるため、穏やかな言い回しに言い換えることが大切です。
- NG表現:死ぬ/亡くなる/終わる/最後/消える/生きていたら
- 代替表現:ご逝去/旅立たれた/ご永眠/故人となられた
2-3. 縁起が悪い数字や語呂(4、9 など)
「四(し)」「九(く)」などの忌み数は、「死」「苦」を連想させる語呂合わせから避けるのが一般的です。
弔電に数字を使う際には、特に配慮が必要です。
- NG表現:4/9/49(例:49本の花)
- 代替表現:5/8/10など、縁起が悪くないとされる数字
2-4. 明るすぎる・祝い事に関する言葉
弔電は哀悼の意を表すものです。「おめでとう」「喜び」などの祝い言葉はふさわしくないため、使用は避けましょう。
- NG表現:おめでとう/祝う/喜び/華やか/楽しい/賑やか/寿/笑顔
- 代替表現:心よりお悔やみ申し上げます/静かにお見送り申し上げます/慎んで哀悼の意を表します
3. 忌み言葉を避けた正しい弔電文面の書き方
弔電は、ご遺族の心に寄り添いながら哀悼の気持ちを丁寧に届けるためのメッセージです。
そのため、直接的すぎる表現や忌み言葉は避けつつ、慎みと敬意のある柔らかな言い回しを心がけましょう。
たとえば、「死ぬ」「終わる」などの直接的な言葉は避け、「ご逝去」「旅立たれた」「ご永眠」などの婉曲的な表現を使用することで、配慮が伝わります。
また、「ご冥福をお祈りします」という言葉は一般的ですが、仏教由来のため神道やキリスト教の方には適さない場合があります。
宗教や宗派が不明な場合には、「心よりお悔やみ申し上げます」など、宗教を問わず使える表現が安心です。
ご家族を気遣う表現としては、「ご遺族の皆さまが心穏やかに過ごせますようお祈り申し上げます」や、「ご家族の皆さまにお力添えが届きますようお祈りいたします」といった文章も適しています。
どのような言葉を選べばよいか迷ったときは、弔電・お悔やみの文例集をご覧ください。
忌み言葉を避けた実例が多数掲載されており、安心してメッセージを作成いただけます。
4. よくある弔電文例の中に含まれやすいNGワード
弔電の文例の中には、一見丁寧に見えても、ご遺族にとって不快に響く可能性のある表現が含まれていることがあります。
ここでは、よく使われがちなNGフレーズと、より配慮のある言い換え例を比較しながらご紹介します。
-
NG例:「ご愁傷さまですが、これも運命ですね」
言い換え例:「心よりお悔やみ申し上げます。皆さまのご心痛はいかばかりかとお察しいたします」 -
NG例:「突然死とは思いませんでした」
言い換え例:「突然の訃報に接し、言葉もございません。静かにご冥福をお祈りいたします」 -
NG例:「とても可哀想でした」
言い換え例:「ご家族の皆さまに、心よりお悔やみ申し上げます」 -
NG例:「これを機にご自愛ください」
言い換え例:「ご家族の皆さまにおかれましては、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます」
思いやりのつもりで使った言葉が、かえってご遺族を傷つけてしまうこともあるため、文面には慎重な配慮が必要です。
不安な場合は、弔電の文例集を参考に、宗教・立場を問わず安心して使える言葉を選びましょう。
5. 初めてでも安心:弔電マナーと言葉選びの基本Q&A
弔電に慣れていない方や文面の表現に迷いがある方へ、忌み言葉やマナー、言い換えに関する代表的な疑問をQ&A形式でわかりやすくご紹介します。
- 弔電で忌み言葉とは何ですか?
-
忌み言葉とは、不幸が繰り返されることや不吉な印象を与える言葉のことを指します。
弔電ではご遺族への心遣いとして、こうした表現は避けるのが基本的なマナーとされています。 - 弔電で避けた方がよい言葉にはどんなものがありますか?
- たとえば、「たびたび」「くれぐれも」「死ぬ」「終わる」「四(し)」「九(く)」などは、不幸の継続や不吉な語感を連想させるため、使用は控えるのが適切です。
- 弔電に使ってはいけないお祝いの言葉はありますか?
- はい。「おめでとう」「祝う」「寿」など祝い事を連想させる言葉は、弔電の内容としてふさわしくないため、避けましょう。
- 弔電の文面に不安がある場合はどうすればいいですか?
- ご安心ください。文例集やマナーガイドをご活用いただくことで、忌み言葉を避けた適切な表現を簡単に選ぶことができます。
- 「ご冥福をお祈りします」はいつ使ってよいのですか?
-
「ご冥福をお祈りします」は仏教由来の表現です。
神道・キリスト教では適さない場合もあるため、宗教が不明な場合は「心よりお悔やみ申し上げます」など、宗派に左右されない表現が安心です。 - 弔電の文末に「ご自愛ください」と書いても大丈夫ですか?
-
「ご自愛ください」は状況によっては不自然に響くことがあります。
弔意を伝えたうえで健康を気遣う場合は、「皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます」など、丁寧で控えめな表現がおすすめです。
6. 関連ページ|文例・マナー解説・迷ったときの判断ガイド
弔電の言葉選びやマナーに不安がある方、さらに丁寧な文面を学びたい方へ、以下のガイドもご活用ください。
迷ったときの判断基準や、実例に基づいた文例も多数掲載しています。