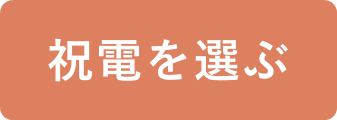弔電で避けるべき忌み言葉・NG表現一覧|失礼のない文面にするための完全ガイド
弔電を送る際、どんな言葉を使えばよいか迷った経験はありませんか?
特に注意が必要なのが、不幸の繰り返しや不吉さを連想させる「忌み言葉」やNG表現です。
何気ない言葉が遺族にとって不快に感じられてしまうこともあるため、正しい言葉選びは弔電マナーの基本といえます。
このページでは、弔電における避けるべき言葉や表現をカテゴリ別にわかりやすく解説するとともに、使っても問題ない言い換え例や、よくある文例の注意点まで丁寧にご紹介します。
初めて弔電を送る方はもちろん、より丁寧な言葉で気持ちを届けたい方にも役立つ実用的な内容です。
1. 忌み言葉とは?弔電における意味と重要性
忌み言葉(いみことば)とは、死や不幸を連想させる言葉や、不吉な意味を含む表現のことを指します。
特に「重ね言葉(たびたび、くれぐれも)」や「直接的な死の表現(死ぬ、終わる)」などは、不幸が繰り返される印象を与えるため、避けるのが礼儀とされています。
弔電は、遺族に対して哀悼の意を丁寧に伝えるためのメッセージです。
そのため、言葉一つひとつに慎重な配慮を込めることが、マナーとして非常に大切になります。
忌み言葉を使わず、落ち着いた表現で気持ちを伝えることで、失礼のない誠意ある弔電となります。
2. 弔電で絶対に避けたい忌み言葉・NG表現の一覧
ここでは、弔電で避けるべき忌み言葉を4つの分類に分けてご紹介します。
それぞれの言葉の例・避ける理由・代替表現を併せて確認し、失礼のない文面づくりの参考にしてください。
2-1. 不幸が繰り返されることを連想させる言葉(重ね言葉)
「たびたび」「くれぐれも」などの重ね言葉は、不幸が続くことを想起させるため、弔電では避けられます。
- NG表現:たびたび/重ね重ね/くれぐれも/いよいよ/次々
- 代替表現:深く/心より/慎んで/このたびは
2-2. 死や終わりを直接的に連想させる言葉
「死ぬ」「終わる」などの直接的表現は、ご遺族の心情を考慮し、配慮ある言い回しに置き換えることが望まれます。
- NG表現:死ぬ/亡くなる/終わる/最後/消える/生きていたら
- 代替表現:ご逝去/旅立たれた/ご永眠/故人となられた
2-3. 縁起が悪い数字や語呂(4、9 など)
「四(し)」「九(く)」などの忌み数は、「死」や「苦」との語呂合わせから避けられます。
特に本数や金額など、数字が入る場合には注意が必要です。
- NG表現:4/9/49(例:49本の花)
- 代替表現:5/8/10など、縁起の良いとされる数字
2-4. 明るすぎる・祝い事に関する言葉
弔電は哀悼の意を伝えるものです。「おめでとう」「喜び」などの祝福表現は場にふさわしくありません。
- NG表現:おめでとう/祝う/喜び/華やか/楽しい/賑やか/寿/笑顔
- 代替表現:心よりお悔やみ申し上げます/静かにお見送り申し上げます/慎んで哀悼の意を表します
3. 忌み言葉を避けた正しい弔電文面の書き方
弔電は、ご遺族の心に寄り添いながら哀悼の気持ちを丁寧に届けるためのものです。
そのため、直接的すぎる表現や忌み言葉は避けつつ、丁寧で柔らかな言い回しを心がけましょう。
たとえば、「死ぬ」「終わる」といった言葉の代わりに、「ご逝去」「旅立たれた」などの婉曲表現を使うと、失礼がなく、より配慮が伝わります。
また、「ご冥福をお祈りします」という言葉は一般的ですが、仏教以外の宗教(神道・キリスト教など)では適さないこともあるため、注意が必要です。
宗教や地域の慣習に不安がある場合は、「心よりお悔やみ申し上げます」や「ご家族の皆さまにお力添えが届きますようお祈りいたします」など、宗教を問わず使える表現を選ぶのが安心です。
どのような表現が適切か迷ったときは、弔電・お悔やみの文例集をご参照ください。
実際に忌み言葉を避けた安心できるメッセージ例を多数ご紹介しています。
4. よくある弔電文例の中に含まれやすいNGワード
弔電文例の中には、一見丁寧に見えても、実は避けたほうがよい表現が紛れていることがあります。
ここでは、使ってしまいがちなNGフレーズと、その言い換え例をご紹介します。
-
NG例:「ご愁傷さまですが、これも運命ですね」
適切な言い換え:「心よりお悔やみ申し上げます。皆さまのご心痛はいかばかりかとお察しいたします」 -
NG例:「突然死とは思いませんでした」
適切な言い換え:「突然の訃報に接し、言葉もございません。静かにご冥福をお祈りいたします」 -
NG例:「とても可哀想でした」
適切な言い換え:「ご家族の皆さまに、心よりお悔やみ申し上げます」 -
NG例:「これを機にご自愛ください」
適切な言い換え:「ご家族の皆さまにおかれましては、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます」
文例作成時には、気遣いのつもりで使った言葉が、かえってご遺族の心を傷つけてしまうこともあります。
迷ったときは、弔電の文例集を活用して、安心して使える文例から選ぶのがおすすめです。
5. 初めてでも安心:弔電マナーと言葉選びの基本Q&A
弔電に慣れていない方や、文面の表現に不安がある方のために、忌み言葉・マナー・言い換えに関するよくある質問をまとめました。
- 弔電で忌み言葉とは何ですか?
- 忌み言葉とは、不幸が繰り返されることや不吉な印象を与える言葉のことです。弔電ではご遺族への配慮として、こうした表現を避けるのが一般的なマナーです。
- 弔電で避けた方がよい言葉にはどんなものがありますか?
- 「たびたび」「くれぐれも」「死ぬ」「終わる」「四(し)」「九(く)」などは、不幸の繰り返しや不吉な印象を連想させるため、弔電では避けるべき言葉とされています。
- 弔電に使ってはいけないお祝いの言葉はありますか?
- はい。「おめでとう」「祝う」「寿」などのお祝いを連想させる言葉は、弔電の文面にはふさわしくないため、使用は避けましょう。
- 弔電の文面に不安がある場合はどうすればいいですか?
- 弔電の表現に迷った際は、文例集やマナーガイドを参考にするのがおすすめです。For-Denpoでは、忌み言葉を避けた文例を多数ご紹介していますので、安心してご利用いただけます。
- 「ご冥福をお祈りします」はいつ使ってよいのですか?
- 「ご冥福をお祈りします」は仏教の表現であり、神道・キリスト教ではふさわしくない場合があります。宗教が不明な場合は「心よりお悔やみ申し上げます」など宗派に依存しない表現を選びましょう。
- 弔電の文末に「ご自愛ください」と書いても大丈夫ですか?
- 「ご自愛ください」は文脈によっては違和感を与えることがあります。お悔やみの後に健康を気遣うなら、「皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます」など、控えめで丁寧な表現が適しています。
6. 関連ページ|文例・マナー解説・迷ったときの判断ガイド
言葉選びに不安がある方や、もっと詳しく弔電のマナーや文例を知りたい方は、以下の関連ページもぜひご覧ください。