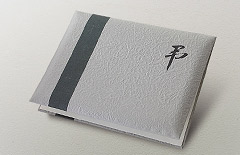弔電の送り方
「葬式に弔電を送りたいけれど、どうすればいいのか分からない」「電報でお悔やみの気持ちを伝えるマナーが知りたい」
このページでは、通夜・葬式・告別式で弔電(電報)を送る際の手順や、宛名・差出人の書き方、失礼にならないメッセージの文例まで、初めての方にもわかりやすくご紹介します。
急な訃報で参列ができない場合でも、葬儀会場やご自宅へ電報を届けることで哀悼の意を丁寧に伝えることができます。
弔電のマナーや注意点を押さえて、心のこもったお悔やみの気持ちを失礼なく届けましょう。
弔電・お悔やみ電報の送り方・打ち方の流れ
弔電(葬式用の電報)は、お通夜・葬儀・告別式のいずれに送っても構いません。
一般的には、告別式や葬儀の場で弔電が読み上げられることが多いため、できるだけ式の前までに届くよう手配するのが望ましいとされています。
その際は、式の日時を事前に確認し、弔電が早く届きすぎないように注意しましょう。
特に、近年増加している家族葬などでは、会場にスタッフが常駐していない場合もあり、喪主様が到着されるまで弔電が受け取れないこともあります。
また、弔電の宛名は必ず喪主様宛にするのがマナーです。
喪主様以外の宛名では、宛先不明となったり、ご遺族に余計な負担をかけてしまう可能性がありますのでご注意ください。
弔電・お悔やみ電報を送る前の確認事項はこちら
弔電・お悔やみ電報の宛名の表記方法についてはこちら
弔電(葬式用電報)の本文では、哀悼の気持ちを丁寧に伝える表現が求められます。
一般的なお悔やみの言葉としては、「ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます」「心よりご冥福をお祈りいたします」などがよく用いられます。
故人と喪主様のご関係に応じて、「ご尊父様」「ご母堂様」などの敬称を加えるのが正式なマナーとされています。
はじめての方でも安心して弔電を作成いただけるよう、文例集やマナーガイドを豊富にご用意しています。
葬式にふさわしい表現・避けるべき言葉なども詳しく解説しておりますので、迷わず適切なメッセージを選ぶことが可能です。
弔電・お悔やみ電報の本文の書き方はこちら
弔電・お悔やみメッセージの文例を見る
弔電・お悔やみ電報は、「台紙から選ぶ」または「文例から選ぶ」のいずれの方法でもお申込みいただけます。
初めての方にも安心してご利用いただけるよう、葬式にふさわしい弔電の選び方や手続き方法を丁寧にご案内しています。
ご用意している商品には、フォーマルな台紙タイプはもちろん、お線香付き・供花付きなど弔意を深く伝えるセットタイプも多数ございます。
故人やご遺族との関係性やシーンに合わせて、文例と一緒に最適な弔電をお選びください。
弔電のご利用手順はこちら
弔電・お悔やみ電報の商品一覧を見る
よくご利用される弔電・お悔やみ電報・供花のご案内
グレー色の地に故人を偲び、薄墨色で「弔」が記された弔電台紙です。
哀悼の想いを込め、静寂を表した落ち着きのある雰囲気の弔電台紙です。
濃紺色の丹後ちりめんに絹糸で刺繍された日本刺繍電報です。
清らかな雰囲気のプリザとお線香がセットになっている弔電です。
ご葬儀・法事・命日などにご利用いただいています。
弔電・お悔やみ電報を送る場面
「弔電(電報)は、お通夜・葬儀・告別式のどの場面に送ればよいのか」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。
基本的に、弔電はどの場面に送っても問題ありませんが、ご葬儀や告別式の際に読み上げられることが一般的なため、式が始まる前に届くように手配するのが望ましいです。
特に最近は、身内のみで執り行う家族葬が増えており、式場に常駐スタッフがいない場合もあります。
電報が早く届きすぎると、ご遺族が到着する前で受け取ってもらえないこともあるため、タイミングには注意が必要です。
「通夜・葬式に間に合うように」「失礼のないタイミングで」弔電を届けるためには、葬儀の日程・時間を正確に確認してから申し込みましょう。
弔電・お悔やみ電報を送る前の確認事項
弔電(葬式用の電報)を確実にお届けするためには、事前の情報確認がとても重要です。
下記の項目は、弔電を申し込む際に必ず必要となる内容です。
誤った情報で申し込むと、宛先不明で届かない、葬儀・告別式に間に合わないといったトラブルにつながる可能性がありますので、正確に確認しましょう。
喪主様のお名前(フルネーム)
故人のお名前
喪主様と故人の関係
通夜・葬儀・告別式の日時と式場(会館・斎場)
送る相手の宗教・宗派
上記を正しく把握したうえで、適切なタイミングと内容で弔電をお申込みください。
弔電・お悔やみ電報はいつまでにお届け
弔電(葬式用の電報)を送るタイミングに明確な決まりはありませんが、
一般的にはご葬儀や告別式の開始前までに届くように手配するのがマナーとされています。
多くの場合、弔電は葬儀や告別式で読み上げられることが多いため、式の前日?当日の午前中を目安に届くよう調整しましょう。
その際には、通夜・葬儀・告別式の日時や会場を事前に確認したうえで、配達可能な時間帯もチェックすることが大切です。
近年では、親族のみで執り行う「家族葬」も増加傾向にあり、式場にスタッフが常駐していないケースもあります。
そのため、あまりに早く弔電が届いてしまうと受け取ってもらえない可能性がありますので、早すぎず遅れないタイミングでの手配が重要です。
弔電・お悔やみ電報の宛名の表記方法について
弔電(葬式用の電報)を送る際の宛名は、故人様ではなく「喪主様」を記載するのが基本です。
弔電は、ご遺族に対して哀悼の意を伝えるためのものであるため、故人宛ではなく喪主様宛に送るのが正式なマナーとなっています。
また、式場(斎場・会館)では喪主様のお名前で葬儀が管理されていることが多く、宛名が喪主様以外の場合は受け取りを断られることや、ご遺族に余計な負担をかけてしまう恐れもあります。
そのため、弔電の宛名は必ず喪主様のフルネームで記載しましょう。
もし、喪主様以外のご親族や関係者に弔電を届けたい場合は、式場でも分かりやすいように
「(喪主名)○○様方 △△様」という形で記載するのが望ましいとされています。
宛名の記載を誤ると失礼にあたるだけでなく、正しく届けられない可能性もあります。
敬意と配慮を込めて、正確かつ丁寧に宛名を記載しましょう。
弔電・お悔やみ電報の差出人の表記方法について
弔電(葬式用の電報)を受け取るご遺族にとって、差出人が誰で、故人とどのような関係だったのかが明確であることは非常に重要です。
特に個人名で送る場合は、故人との関係性をひとこと添えることで、より丁寧で心のこもった印象になります。
例えば、次のように記載すると分かりやすくなります。
差出人例:山田 太郎(株式会社○○ △△年入社同期一同)
差出人例:佐藤 花子(ご近所の者として)
差出人例:田中 一郎(高校時代の恩師)
法人名義で弔電を送る場合は、会社名や役職名を含めることで、信頼性と敬意を保った表記が可能です。
例:株式会社○○ 代表取締役 山田 太郎
故人やご遺族に失礼のないよう、差出人の表記は正確かつ配慮ある内容にすることを心がけましょう。
弔電の台紙の選び方
大切な方やそのご家族のご逝去に際して、通夜や葬儀に参列できない場合は、弔電(お悔やみ電報)で哀悼の意を伝えることが一般的です。
弔電を送る際、どのような電報の台紙を選べばよいか迷う方も少なくありません。
以前は、落ち着いた色味のシンプルな台紙が主流でしたが、近年では以下のように用途や相手に応じた選択肢が広がっています。
● プリザーブドフラワー付きの弔電:受け取った後も飾っていただけるため、ご遺族の心を癒す贈り物として人気です。
● お線香付きの弔電:参列できない代わりに「お焼香の気持ち」を添えて伝える形式として選ばれています。
● 供花付きの弔電:会社関係や取引先など、格式を重んじる場面で、故人への敬意を表す方法として利用されます。
台紙を選ぶ際は、故人との関係性、ご遺族の立場、葬儀の形式(家族葬・社葬など)、相手の宗教・宗派などを考慮しましょう。
気持ちを丁寧に伝えるためにも、形式だけにとらわれず、受け取る方に寄り添った台紙・仕様を選ぶことが大切です。
弔電・お悔やみ電報の本文の書き方について
弔電(葬式用の電報)の本文には、哀悼の意を表す丁寧な言葉を用いるのが一般的です。
よく使われる表現としては、
「ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。」
「ご逝去を悼み、心よりご冥福をお祈りいたします。」などがあります。
故人と喪主様との関係性に応じて、「ご尊父様」「ご母堂様」「ご令息様」などの敬称を添えるのが適切です。
例えば、お父様がご逝去された場合は「ご尊父様のご逝去を悼み~」といった書き出しがよく使われます。
基本的には短くても心のこもった表現を心がけ、「お悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈りいたします」といった言葉を入れると丁寧な印象になります。
【弔電本文を記載する際の注意点】
メッセージを作成する際は、以下の点にご注意ください:
● 誤字・脱字がないかを必ず確認しましょう。
● 忌み言葉(不幸や死を連想させる重ね言葉や不吉な語)は使用しないようにします。
● 宗教に配慮した表現を心がけましょう。特にキリスト教式の葬儀では「冥福」「成仏」など仏教用語は避けます。
● プレビュー画面でレイアウトや印刷イメージを事前に確認するのも安心です。
避けた方がよい言葉の例
◆ 悪いことを連想させる表現:
とんでもないこと、とんだこと
◆ 不幸が繰り返されることを連想させる表現:
しばしば、たびたび、またまた、重ね重ね、つづいて、繰り返す、次々、再び
◆ キリスト教式で避けたい表現:
お悔やみ、冥福、ご愁傷様、供養、往生、成仏、弔う
◆ 不吉な音の言葉:
「九」「四」など(語呂が「苦」「死」を連想させる)
正しいマナーを守って弔電をお送りすることで、形式だけでなく心のこもった哀悼の意を丁寧に伝えることができます。
友人に送る弔電・お悔やみ電報メッセージ文例|葬式に電報を送る際の参考に
大切なご友人のご逝去に際し、葬式に参列できない場合は「弔電(お悔やみ電報)」で哀悼の意を伝えることが一般的です。
ここでは、友人の葬式にふさわしい弔電メッセージ文例をご紹介します。
突然の別れに言葉が見つからない方でも、心のこもった電報を送れるように、文面の参考としてご利用ください。
大切なご友人の突然の訃報に、言葉が見つかりません。
○○は学生時代からの親友でした。
すぐに駆けつけたい気持ちでいっぱいですが、遠方よりお悔やみ申し上げます。
安らかなるご永眠をお祈りいたします。
ご友人の突然のご逝去に接し、深い悲しみに包まれております。
まだ話したいことがたくさんあっただけに、残念でなりません。
在りし日のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈りいたします。
一番の友人だった○○の訃報に接し、悲しさで胸がいっぱいです。
これまでの思い出は今も心に残っています。
お別れの言葉を直接伝えられないことが悔やまれますが、
遠くから安らかな旅立ちをお祈りしております。
古くからの友人を失い、深い喪失感を抱いております。
葬儀に参列できず、直接お別れができないのが心残りです。
これまでの感謝とともに、ご冥福をお祈り申し上げます。
幼なじみだった○○の訃報に接し、ただ驚くばかりです。
小さなころの思い出が次々に浮かんできます。
どうか安らかにお眠りください。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
親戚に送る弔電・お悔やみ電報メッセージ文例|葬式にふさわしい文面とは
親戚のご不幸を知った際、葬式に参列できない場合には、弔電(お悔やみ電報)で哀悼の意を伝えるのが礼儀とされています。
ここでは、叔父・叔母・従兄弟・義理の家族など親戚に向けた電報メッセージ文例をご紹介します。
「失礼のない言葉を使いたい」「家族向けの電報の例が知りたい」とお考えの方は、ぜひご参考ください。
ご逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます。
親戚一同が集まった際に、いつも温かく迎えてくださった○○様の笑顔が忘れられません。
お別れに伺えず申し訳ありませんが、どうか安らかにお眠りください。
従妹○○の突然の訃報に、深い悲しみを覚えております。
特に親しくさせていただいていたこともあり、数々の思い出が胸をよぎります。
心よりご冥福をお祈りいたします。
ご親戚を支えてこられた○○様の訃報に接し、ただ驚いております。
その頼もしさと温かさに、心より感謝しております。
ご恩に報いることもできず残念ですが、遠方よりご冥福をお祈り申し上げます。
ご主人様のご逝去を知り、心からお悔やみ申し上げます。
ご家族のお悲しみは察するに余りあるものと存じます。
安らかな旅立ちとなりますよう、心よりお祈りいたします。
突然のご訃報に接し、驚きを禁じ得ません。
子どものころ、親戚の集まりで楽しく過ごした日々が思い出されます。
在りし日のお姿を偲び、哀悼の意を捧げます。
ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
○○様の生前のご活躍は、親戚として誇らしく感じておりました。
ご冥福をお祈り申し上げるとともに、お別れに伺えず残念でなりません。
幼い頃、○○様に連れて行っていただいた家族旅行が、今でも心に残っています。
穏やかな笑顔を思い出し、在りし日を偲びながら、心よりご冥福をお祈りいたします。
突然の訃報に接し、深い悲しみに包まれております。
いつも優しくしてくれた○○叔父様のご恩に、今あらためて感謝いたします。
安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます。
弔電・お悔やみ電報で使われる敬称について|葬式の電報マナー
弔電(葬式用の電報)を送る際には、故人と受取人との関係性に応じた「敬称」を正しく使うことが大切です。
とくにお悔やみ電報では、形式を重んじる場面も多く、相手に失礼のない適切な言い回しを選ぶことが重要です。
以下に、続柄別でよく使われる敬称をまとめましたので、電報の本文作成時や文例選びの参考にしてください。
| 故人との関係 | 使用される敬称例 |
|---|---|
| 実の父 | ご尊父様 / お父様 / お父上様 |
| 実の母 | ご母堂様 / お母様 / お母上様 |
| 夫 | ご主人様 / ご夫君様 |
| 妻 | ご令室様 / ご令閨様 / 奥様 |
| 祖父・祖母 | ご祖父様 / ご祖母様 / お祖父様 / お祖母様 |
| 息子・娘 | ご子息様 / ご令息様 / ご息女様 / ご令嬢様 |
| 兄弟姉妹 | ご令兄様 / ご令姉様 / ご令弟様 / ご令妹様 |
| 伯父・叔父 | 伯父様 / 伯父上様 / 叔父様 / 叔父上様 |
| 伯母・叔母 | 伯母様 / 伯母上様 / 叔母様 / 叔母上様 |
| 家族全体 | ご家族様 / ご一同様 / 皆様 |
敬称を間違えると、ご遺族に対して無礼にあたる可能性もあるため、事前に関係性を確認し、正しい敬称を用いるようにしましょう。
続柄別の詳しい文例は、以下のリンクからもご覧いただけます。
お葬式に贈る弔電・お悔やみ文例集はこちら
社葬に送る弔電・お悔やみ電報について|宛名・差出人・文面の注意点
社葬(企業主催の葬儀)に弔電を送る場合も、基本的な電報マナーは一般葬と同様です。
ただし、ビジネスシーン特有の慣習や表現上の配慮が必要になります。
以下に、社葬で弔電を送る際の宛名・差出人・本文表現のポイントをまとめました。
【宛名の表記方法】
社葬では、ご葬儀の主催が企業であるため、喪主様ではなく「葬儀責任者」や企業名宛にするのが一般的です。
例:株式会社〇〇 故△△様 葬儀責任者様
受取人が不明な場合は、「株式会社〇〇 御中」で送るケースもあります。
【差出人の書き方】
弔電の差出人が法人の場合は、代表者名または部署名を明記します。
重要な取引先や関係の深い企業であれば、複数名義で送ることも可能です。
例:株式会社〇〇 代表取締役 △△
例:株式会社〇〇 営業部一同
【社葬にふさわしい弔電本文の例】
「貴社 ○○様のご逝去の報に接し、社員ご一同様のご心痛、いかばかりかとお察し申し上げます。
生前のご功績に深く敬意を表するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。」
社葬においては、弔意を丁寧に伝えると同時に、企業間の礼儀を重視した表現が求められます。
電報の宛先・差出人・文面に配慮することで、ビジネスマナーを損なわず、誠意を伝えることができます。
法要に送る弔電・お悔やみ電報について|命日・法事の弔意を伝える方法
法要(四十九日・一周忌・三回忌など)においても、弔電(お悔やみ電報)を送ることは丁寧な弔意の表現として適しています。
基本的な送り方・マナーは葬儀用の弔電と同様ですが、文面には「法要に寄せて」などの表現を入れると、より気遣いが伝わります。
【法要に送る電報のタイミング】
法要の前日または当日午前中までに届くよう手配するのが一般的です。
とくに自宅や菩提寺宛てに送る場合は、受取人の名前や会場住所を正確に記載するよう注意しましょう。
【法要向けの弔電メッセージ例】
「〇〇様のご法要に際し、心より哀悼の意を表します。
生前のご厚情に感謝を申し上げるとともに、故人のご冥福をお祈りいたします。」
「ご法要の折、心ばかりの弔意を申し上げます。
故人の安らかなご冥福を、心よりお祈り申し上げます。」
忙しくて参列できない場合でも、法要の場に電報を届けることで、ご遺族に思いやりの気持ちをしっかり伝えることができます。
命日・法事・法要など、タイミングに応じた弔電の送り方について迷われた際は、ぜひ文例集もご参考ください。