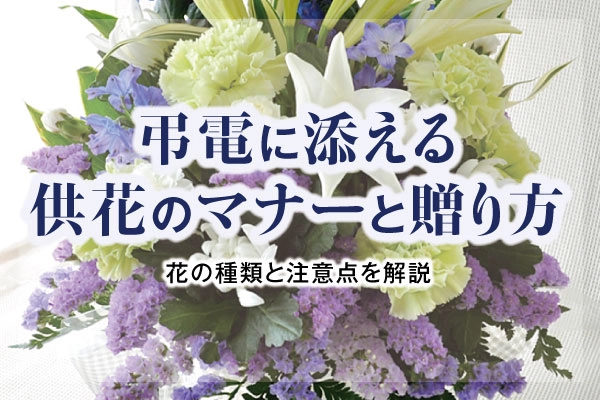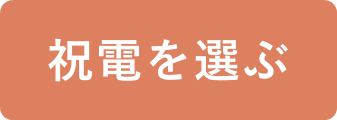弔電に添える供花のマナーと贈り方|花の種類と注意点を解説
供花(くげ/きょうか)とは、通夜や葬儀、告別式、法要などで、故人への哀悼の気持ちを花に託して贈る日本独自の弔意表現です。
このページでは、供花を贈るときの基本的なマナーや送り方の注意点、宗教・宗派ごとの違いや弔電との組み合わせ方について、初めての方にもわかりやすく解説します。
「供花を贈りたいけれど、どんな花がよい?」「失礼のない贈り方は?」と迷っている方のために、実際に多くの方が選んでいる供花の種類や相場もご紹介しています。
供花とは?お悔やみの花に込められた意味
供花とは、故人を偲び、ご遺族へ哀悼の意を示すために贈る生花のことを指します。
主に白や淡い色を基調とした花が選ばれ、清らかさや静けさ、祈りの心を象徴する意味が込められています。
地域や宗教によって供花の形式は異なりますが、共通するのは「花を通じて心を伝える」という弔意の表現です。
また、弔電と一緒に供花を贈ることで、文字だけでは伝えきれない気持ちや想いを、より深く届けることができます。
宗教・宗派によって異なる供花のしきたり
供花を贈る際には、相手の宗教・宗派に応じた形式を尊重することが大切です。
宗教によって「適した花の種類」や「供え方の意味合い」が異なるため、誤解を避けるためにも事前の確認や基本マナーの理解が必要です。
以下に、日本でよく見られる3つの宗教ごとの供花の特徴をまとめました。
| 宗教・宗派 | 供花の特徴 |
|---|---|
| 仏教 | 白を基調とした落ち着いた花が基本。菊、百合、胡蝶蘭などがよく使われ、「浄土」や「冥福」を祈る意味が込められます。 |
| 神道 | 榊(さかき)や白い花が中心。故人は神として祀られるため、供花は供物としての意味を強く持ちます。 |
| キリスト教 | 洋花を用いた白中心のアレンジメントが一般的。カーネーションやユリなどが選ばれ、「祈り」や「魂の安らぎ」を表します。 |
不安な場合は、事前に葬儀社や喪主へ宗教・宗派の確認を取ると安心です。
宗教に合った供花を贈ることは、弔意を正しく丁寧に伝える第一歩となります。
供花を贈るタイミングと送り先の選び方
供花は通夜や葬儀の場に間に合うように届けるのが基本です。
最も丁寧なのは、通夜の前日または当日午前中に到着するよう手配することです。
また、供花の送り先は葬儀が行われる場所に応じて変わります。
葬儀場・ご自宅・斎場・寺院など、どこに送るべきかは事前に喪主や葬儀社に確認しておきましょう。
近年では、ご遺族の意向によって「供花はご辞退申し上げます」とするケースも増えています。
そのため、供花を贈る前には必ず相手の意向を確認することがマナーです。
供花に適した花と避けたほうがよい花
供花には白や淡い色を基調とした花が適しています。
菊、百合、カーネーション、胡蝶蘭などは定番であり、落ち着きと哀悼の意を込めるのにふさわしい花とされています。
一方で、赤いバラ(トゲがあるため)や香りが強すぎる花、毒性のある植物(例:スズラン)は避けるべきとされています。
また、色彩や香りが華やかすぎる花は葬儀の場にふさわしくないと受け取られる可能性があるため注意が必要です。
弔電と一緒に供花を贈る際の注意点
弔電と供花を併せて贈る場合、弔電の文面に「供花をお贈りいたします」と添えることで、相手に配慮の気持ちが伝わります。
メッセージに供花の意図を明記することで、ご遺族にもより丁寧な印象を与えられます。
弔電と供花は別々に届いてもマナー違反にはなりませんが、可能であれば同じ日・近い時間帯に届くよう手配するのが理想です。
時間の調整が難しい場合でも、どちらも式の前に届くようにすることで問題ありません。
また、最近では弔電と供花を一緒に注文できるサービスも増えており、遠方からでも一括で弔意を届けることが可能です。
手配の手間を省きつつ、誠意のあるお悔やみを伝える方法として多く利用されています。
供花に添える名札の書き方と相場の目安
供花を贈る際は、差出人を明記した名札(名札札・立て札)を添えるのが一般的です。
名札の記載内容は、個人名・会社名・肩書きなど、送り手の立場に応じて使い分けます。
名札の基本的な書き方
- 個人で贈る場合:「山田 太郎」「山田家一同」など、フルネームまたは家名で表記
- 連名で贈る場合:2~3名までの個人名を並列で記載。それ以上は「○○有志一同」などと記す
- 法人・団体で贈る場合:「株式会社○○ 代表取締役 山田 太郎」のように会社名・役職・氏名の順に記載
供花の相場の目安
供花の価格は、おおよそ1基あたり5,000円~20,000円程度が相場です。
地域や葬儀の規模によっても異なりますが、最も多いのは1基10,000円前後のスタンド花やアレンジメントです。
※「1基(いっき)」とは、供花を1単位で数える表現です(左右1対で贈る場合は「2基」となります)。
弔意の気持ちを丁寧に伝えるためにも、名札の記載ミスや不適切な肩書きに注意しましょう。
不安な場合は、注文先に正しい名札の書式を相談するのも安心です。
贈られた側のマナー(お返し・お礼状など)
供花を受け取った側には、お悔やみの気持ちをいただいたことに対する感謝の気持ちを示すマナーがあります。
状況に応じて、お礼状の送付や香典返しなどを検討しましょう。
お礼状の基本
弔電や供花をいただいた方に対しては、葬儀後なるべく早く、1週間以内を目安にお礼状を出すのが一般的です。
定型文でも問題ありませんが、手書きや個別の一文を添えることで、より丁寧な印象になります。
お返し(香典返し)との関係
供花をいただいた場合、お返しは基本的に不要とされていますが、香典とともに供花を受け取った場合は、香典返しに含めて対応することが一般的です。
地域や風習によっても異なるため、葬儀社や親族と相談しながら決めると安心です。
連絡・確認の際の注意点
- お礼状や返礼品は、故人の名前・喪主の名前を正確に記載するようにしましょう。
- 供花の差出人が不明な場合は、葬儀社などに確認してから対応するのが無難です。
- 香典辞退・供花辞退を表明していた場合でも、届いたものには何らかの感謝の意を示すことが望ましいです。
よくある質問(FAQ)
Q. 供花は誰宛に送ればよいですか?
A. 一般的には喪主宛に送るのが基本です。喪主が不明な場合や関係が近くない場合は、「〇〇家ご一同様」としても失礼になりません。
Q. 弔電と供花は同じ日に届くべきでしょうか?
A. 必須ではありませんが、通夜や葬儀に合わせて同日に届くよう手配すると、より丁寧な印象を与えることができます。
Q. 自宅に供花を送るときに気をつけることはありますか?
A. ご遺族の負担を軽くするため、あまり大きすぎないサイズの花や、香りが強すぎない花を選ぶと良いでしょう。置き場所や配送時間にも配慮するのがマナーです。
電報付き供花ギフトのおすすめ
弔意の気持ちを、花とメッセージの両方で丁寧に届けたい方へ。
供花と弔電をセットで贈れる電報ギフトなら、葬儀や法要の場面でも安心して想いを届けられます。
遠方から参列できない場合や、落ち着いた印象の供花を選びたい方にも好評です。